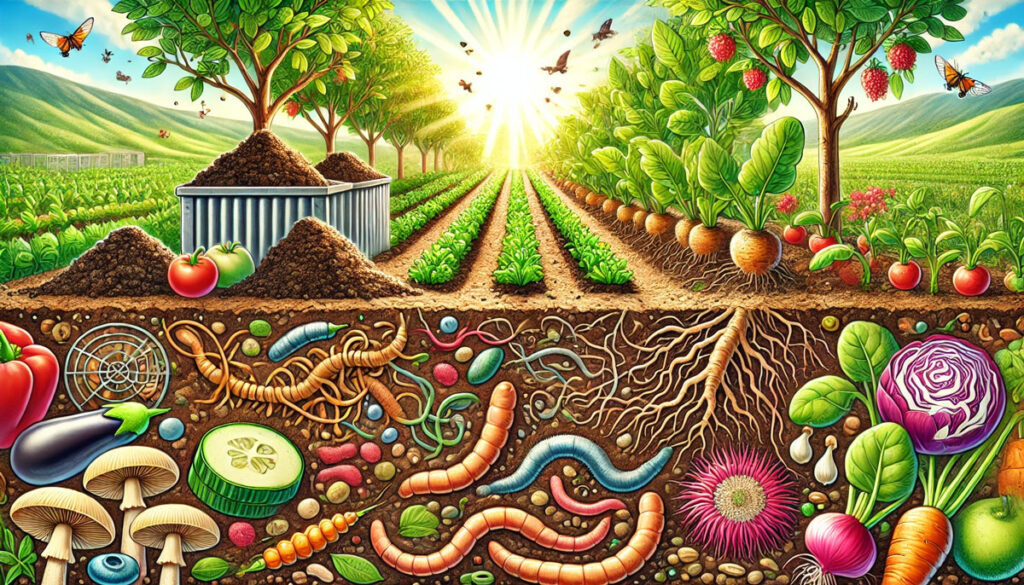自然栽培に興味はあるけれど、どの種を選べばいいの?そんな疑問を抱く方は少なくありません。
本記事では、固定種や在来種が自然栽培に向いている理由を、実践者の声や地域の事例を交えながら紹介します。
誰でも始められる“固定種ライフ”の第一歩として、種選びの背景や育て方の工夫も丁寧に解説しています。
自然とつながり、命をつなぐ食を選びたい方にとって、きっと新たな視点が得られるはずです。
自然栽培と“固定種・在来種”の関係とは?
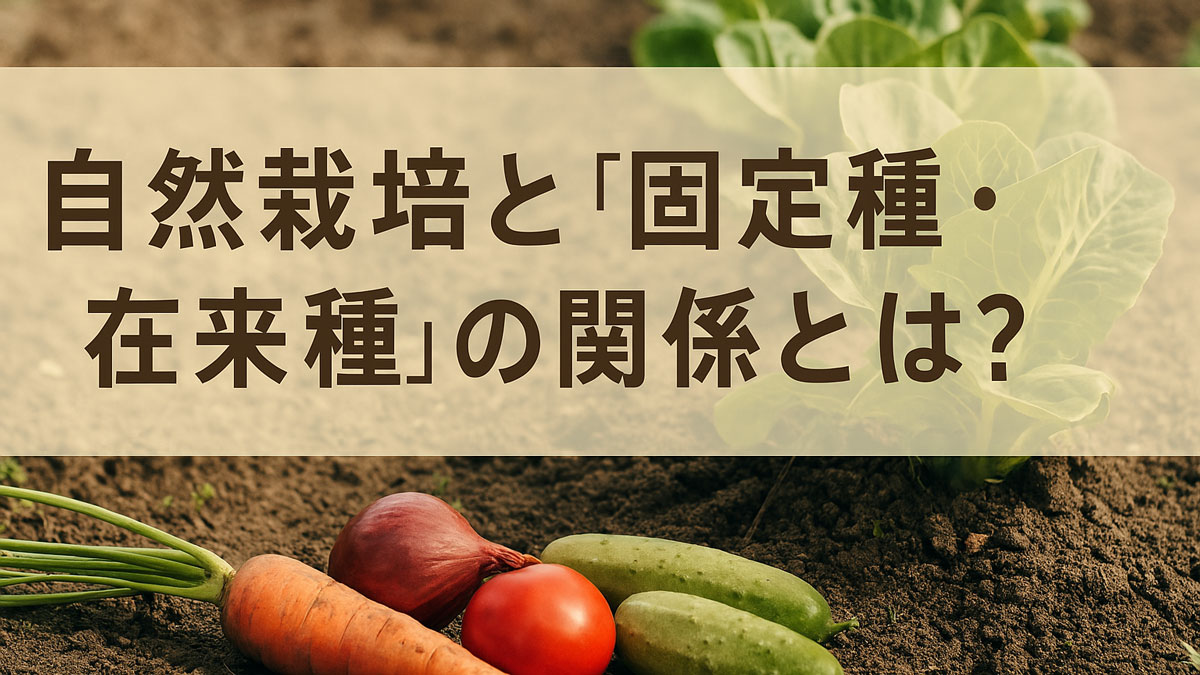
自然栽培とは?農薬も肥料も使わない農法の基本
自然栽培とは、農薬や化学肥料、有機肥料さえも使わず、土の本来の力と自然の循環を最大限に活かして作物を育てる農法です。土壌微生物や作物自身の生命力を引き出しながら、自然界のバランスを乱さずに栽培するのが特徴です。
この農法は、環境負荷が少なく、持続可能な食の未来を支える方法として、近年注目を集めています。しかし、自然栽培は育てる作物を選びます。どんな種でもうまく育つわけではなく、自然の条件に適応しやすい品種の選定が、成功のカギとなります。
そこで重要になるのが、“固定種”や“在来種”の存在です。
“固定種”と“在来種”の違いと定義をわかりやすく解説
一般のスーパーで流通している多くの野菜は、いわゆる「F1種(交配種)」と呼ばれるものです。これは異なる親品種を掛け合わせ、均一な形や成長速度、病害への強さなどを持つように設計されたもの。しかし、自然栽培にはこのF1種が必ずしも向いているとは限りません。
“固定種”とは、人の手で何世代にもわたって選抜・育成された種であり、自然交配によっても親と似た形質を持つのが特徴です。つまり、種を自分で採って、翌年また育てられるという再現性があります。
一方、“在来種”は特定の地域で長い間その土地の風土や文化と共に育まれてきた品種を指します。固定種の一種ではありますが、より地域性が強く、気候や土壌、食文化と密接に結びついています。
固定種=品種としての性質が固定されている
在来種=その土地の風土と文化に根づいた固定種
というイメージを持つと、理解しやすいでしょう。
なぜ自然栽培ではF1種より固定種・在来種が合うのか?
F1種は、均一な収量を求める現代農業では非常に便利な存在です。しかしその反面、外部からの肥料や農薬などのサポートがなければ、本来の力を発揮しづらいという面もあります。つまり、人間の手が多く加えられることを前提に設計されているのです。
一方、固定種や在来種は、自然環境の中で多様な変化に耐え、進化してきた種です。水やりが少なかった年、病気が出た年、虫が多かった年…それでも生き延びた株から種を採り続けることで、その土地の気候に適応しやすい遺伝的特徴が蓄積されます。
特に在来種は、その土地ならではの風味や香りを持ち、「本当の野菜の味がする」と評価されることも少なくありません。自然栽培においては、味や生命力、そして種を残せるという“循環”の考え方が非常に重要です。
さらに、固定種・在来種を育てることは、単なる栽培の選択ではなく、“地域の種を守る”という文化的な営みにもつながります。
まとめると、自然栽培においては、
-
農薬や肥料を必要としない強さ
-
土地に適応する進化の可能性
-
味や香りの個性
-
種をつなぐ循環性
という理由から、F1種ではなく固定種・在来種が真価を発揮します。次の章では、実際にこれらの種を使って育てている農家の事例や、味や育て方のポイントに迫っていきます。
育て方の特徴|固定種・在来種ならではの工夫

発芽のばらつき・個性を活かした栽培のコツ
固定種や在来種の栽培では、発芽や生育スピードにばらつきがあることが一般的です。F1種のようにすべての苗が一斉に育つわけではなく、一本一本がまるで“個性”を持っているかのように違った表情を見せます。
これは一見、栽培の手間を増やすようにも見えますが、自然環境に適応しやすい形質を残すための「多様性」の証でもあります。そのため、均一な管理よりも、それぞれの苗に合わせた間引きや誘引、間作(他の作物と組み合わせる)などの工夫が求められます。
また、発芽率に不安がある場合は、発芽試験や温度調整をしながら、しっかりと準備を整えるのもコツのひとつ。苗作りの段階からていねいに向き合うことで、土の力と作物の個性が共鳴する環境を作ることができます。
自然交配と自家採種のサイクルを回すための注意点
固定種や在来種を育てる醍醐味のひとつが“自家採種”です。毎年タネを採って育て続けることで、その土地に合った作物へと“進化”していく過程を楽しめます。
ただし、ここで注意すべきは交雑(こうざつ)です。同じ科の別品種が近くにあると自然交配してしまい、翌年に性質の異なるタネができてしまう可能性があります。これを避けるためには、
-
距離を離す(目安:10〜20m以上)
-
交雑しやすい野菜(例:カボチャ、ナスなど)は1品種に絞る
-
ネットをかける、隔離栽培をする
といった工夫が必要です。
また、自家採種では種の選抜も大切な作業です。その年に最も元気に育った株からタネを採ることで、年々その品種の適応力を高めることができます。これは単に栽培ではなく、“育種(いくしゅ)”という営みにもつながっていくのです。
トラブル時も農薬に頼らない方法とは?
自然栽培では農薬を使わないため、病害虫との向き合い方にも工夫が求められます。固定種・在来種には、もともと環境に対する耐性が強い品種も多いですが、それでも被害がゼロとは限りません。
そこで活躍するのが、予防と多様性を意識した環境づくりです。
-
混植・輪作で害虫の定着を防ぐ
-
天敵昆虫(テントウムシなど)を呼び込む植栽
-
米ぬか・木酢液・唐辛子エキスなど自然素材の自作スプレー
などを用い、作物自体の免疫力と畑の生態系のバランスを保つことが重要です。
また、被害が出たときには「全部守る」ではなく「育つ力を信じる」という姿勢も大切です。一部を犠牲にしてでも、元気な株を残すことで、翌年にその強さをつなぐことができます。
自然栽培において固定種や在来種を育てるには、「均一さ」や「効率」ではなく、個性と自然との対話が求められます。それはまるで、人と植物が共に育つ時間を共有するような営み。
このような手間と工夫の積み重ねが、“味”や“物語”を持つ野菜を生み出し、種を未来へとつなぐ力になるのです。
地域に根づく在来種のストーリー

各地で守られてきた伝統野菜の例
在来種とは、その土地の風土と共に生きてきた、地域に根ざした種のことです。派手な姿や大量生産には向かないかもしれませんが、それぞれに独自の味や育ち方、ストーリーを持っています。
例えば、**京都の「聖護院かぶ」や「鹿ヶ谷かぼちゃ」**は、江戸時代から伝わる京野菜の代表格。地元の料理文化と密接に結びつき、味噌仕立ての煮物や漬物などに使われてきました。
また、**青森の「津軽みそなす」や島根の「石見銀山いも」**なども、昔からその地域でしか作られていなかった野菜です。厳しい冬を乗り越えられる力、乾燥に強い性質など、土地ごとの気候に適応した“生きた知恵”が詰まっています。
これらの在来種は、ただの作物ではなく、土地の風景や暮らしを物語る文化財ともいえる存在です。
地域文化や食の記憶とつながる種の価値
在来種が大切にされる理由は、味や見た目だけではありません。その種には、地域の暮らしや家族の記憶、伝統行事などが深く関わっているからです。
たとえば、ある地域では毎年秋になると、「○○豆の収穫祭」が行われ、集落の人々が一緒に煮豆を炊いて分け合う。あるいは、正月料理に欠かせない「在来大根」が、何世代にもわたって家族の食卓を支えてきた。
こうした“種を受け継ぐこと”は、食文化だけでなく、人と人とのつながりも受け継ぐ営みなのです。
また、年配の方が「この野菜は昔うちの庭で育ててたよ」と懐かしむことも多く、在来種は記憶を呼び覚ます“食のタイムカプセル”でもあります。
タネから地域を見直す“ローカルフード”の視点
近年、地方創生やエシカル消費の文脈で、「ローカルフード(地元食)」への注目が高まっています。そこでも在来種の存在が大きな意味を持っています。
地域で採れた種を地域で育て、地域で食べる。この循環は、輸送エネルギーの削減や地域経済の活性化といったメリットも生みます。さらに、種の保存活動を通して、地元の若者が農業や食に関心を持つきっかけになることもあります。
たとえば、ある町では「在来野菜マップ」を作成し、道の駅や直売所で「この野菜は○○さんが守ってきた種です」と掲示する試みが行われています。そこに込められているのは、「地元の食文化を知り、支え、次の世代へつなぐ」という強い想いです。
このように、タネを軸にした“まちづくり”や“食育”の広がりは、今や全国各地で始まっているのです。
在来種の魅力は、育てやすさや収量の多さでは測れません。その種が土地とともに生きてきた時間と、そこに込められた人々の想いが、何よりの価値です。
自然栽培という方法は、そうした在来種の力を最大限に引き出す舞台でもあります。「どんな種を選ぶか」は、「どんな未来を選ぶか」とも言えるかもしれません。
次回は、タネを未来へとつなぐために欠かせない“種を守る持続可能性”について深掘りしていきます。
実践者の声|固定種・在来種で変わった自然栽培の現場

農家インタビュー:Aさんが語る「味の深みと手応え」
静岡県で自然栽培に取り組む農家・Aさんは、数年前にF1種から固定種・在来種へと切り替えたことで、大きな変化を感じたといいます。
「最初は育ちにくくて大変でした。でも、2年目から少しずつ畑が応えてくれるようになった」と語るAさん。中でも印象的だったのは、収穫した野菜の“味の深み”。例えば固定種のトマトは、酸味と甘みのバランスがとれていて、市販の品種とはまったく違うと驚かれたそうです。
また、在来のナスを育てたときは、収穫量こそ多くなかったものの、「煮崩れしにくく、味がしみ込む」と地域の飲食店からも高評価。Aさん自身も「手がかかるけど、やればやるほど面白い」と語り、“作物を育てる”というより、“命と対話している”感覚になったと言います。
消費者の反応:「本物の野菜の味がする」という感想
Aさんの野菜を購入した消費者からも、明確な反応が返ってきました。特に家庭で料理する人たちからは、
-
「野菜だけでだしがいらないほど味が濃い」
-
「昔食べた野菜の味を思い出した」
-
「子どもが普段食べないピーマンをパクパク食べた」
といった声が届いているといいます。
こうした感想に共通するのは、「味が違う」という実感。これは単なる品種の違いだけではなく、固定種・在来種のもつ本来の個性と、自然栽培が引き出す力の相乗効果とも言えるでしょう。
最近では、スーパーや通販でも自然栽培・固定種と明記された野菜の取り扱いが増えていますが、実際に食べた人が感動をもって再購入するケースが多く、「食に価値を見出す消費」が広がっていることを感じさせます。
教育や福祉分野での活用事例
自然栽培と固定種・在来種の組み合わせは、単なる農業技術ではなく“教育的・社会的価値”としても注目されています。
たとえば、長野県のある小学校では、地域に伝わる在来の豆を子どもたちと一緒に育て、収穫・調理・保存までを行う「種の授業」を実施。種を取るまでのサイクルを体験することで、命のつながりや食のありがたさを実感する教育になっているそうです。
また、福祉施設でも、知的障がいのある利用者と共に、固定種の野菜づくりに取り組む事例が増えています。育ちがゆっくりな在来種の栽培は、作業の速度よりも丁寧さを大切にできる環境と相性が良いのです。利用者が「自分の育てた野菜が売れた」と喜ぶ姿は、自己肯定感の向上にもつながっています。
このように、固定種・在来種の自然栽培は「生産」「消費」だけでなく「教育」や「福祉」にも広がりつつあるのが現状です。
土と人、種と地域、育てる人と食べる人──それぞれの距離が近づくことで、単なる“野菜づくり”が、“未来の土台づくり”に変わっていくのかもしれません。
次章では、こうした活動がもたらす「持続可能な未来」について、種の多様性と気候変動への備えという視点から掘り下げていきます。
種をつなぐことが未来を守る|持続可能性の視点から

遺伝子多様性と気候変動への適応力
近年、農業においても気候変動の影響が顕著になりつつあります。予測できない高温や豪雨、干ばつなどにより、従来の栽培方法や作物ではうまく対応できない場面が増えています。
このような環境の変化に対応する鍵のひとつが「遺伝子多様性」です。固定種・在来種は、F1種のように均一な性質ではなく、個体ごとに微妙な違い(=遺伝的ばらつき)を持っているため、環境ストレスに対する耐性が高いとされています。
たとえば、ある年に病気に強い株が生き残り、別の年には暑さに強い株が種を残す。こうして環境に応じた自然選抜のサイクルが生まれ、その土地に最適化された“未来を生き抜く力”が蓄積されていくのです。
このような多様性のある種を育て続けることは、気候危機の時代において重要な「生存戦略」と言えるでしょう。
企業種子依存からの脱却=食の主権を取り戻す
現在、日本国内に流通する多くの野菜種子は、一部の大手企業が開発・販売するF1種に依存しています。これらの種は再利用できず、毎年新たに購入しなければならないという特徴があります。
これは農家にとって経済的な負担となるだけでなく、“食の主権”が企業に握られてしまう構造とも言えます。種を自分で採れない=作物の命の源を自分でコントロールできない状態なのです。
対して、固定種・在来種は自家採種が可能。農家や市民が自ら種を採り、次の世代へつなぐことで、地域単位で食の自由と自立を守ることができます。
この種の自立性は、国際的にも「フードソブリンティ(食の主権)」という概念で注目されています。特に自然栽培との相性が良く、「買わない」「奪われない」「育てて守る」という価値観は、今後の社会においてますます重要になるでしょう。
家庭菜園でもできる“固定種ライフ”の始め方
種の保存や多様性というと難しく聞こえるかもしれませんが、実は家庭菜園レベルでも十分に取り組むことができます。
まずは、固定種・在来種の野菜タネを扱う種苗店や通販サイトで購入することから始めましょう。最近では「たねの森」「野口種苗研究所」など、信頼できる固定種専門の販売元が増えています。
次に、自家採種しやすい作物からトライするのがおすすめ。初心者には以下のような品種が向いています。
| 作物 | 種採りの難易度 | 特徴 |
|---|---|---|
| ミニトマト | ★☆☆(かんたん) | 果実ごと採種しやすい |
| 大根 | ★★☆(ふつう) | 2年目に花が咲くが保存しやすい |
| 枝豆 | ★☆☆(かんたん) | 乾燥させてそのまま保存可能 |
こうした“固定種ライフ”を始めることで、育てる楽しさに加えて、命をつなぐ実感や、自分で未来を育てているという喜びを感じられるようになります。
また、子どもと一緒にタネをまき、育て、採る体験は、食育にも最適です。固定種栽培は決して特別な人だけのものではなく、誰もが家庭で始められるサステナブルな一歩なのです。
自然栽培と固定種・在来種は、味や文化を守るだけでなく、**未来の気候や社会に備えるための“希望の種”**でもあります。
種を自分の手で守り、つなぎ、分かち合うこと。それは、ただの栽培技術ではなく、「どう生きるか」を問い直す暮らし方そのもの。
私たち一人ひとりが選ぶタネが、これからの地球と食卓をかたちづくっていくのです。
まとめ|“固定種・在来種”は自然栽培の心と未来
自然栽培という農法は、単に農薬や肥料を使わない“手間のかかる栽培方法”ではありません。むしろそこには、自然と共にある暮らし方や、命をつなぐ哲学が込められています。そして、その価値をもっとも体現しているのが、“固定種”と“在来種”という存在です。
固定種は、長年にわたって人の手と自然の力で育まれ、個性豊かで命の強さを内包しています。在来種は、地域の文化や風土とともに歩んできた、まさに“食の文化財”。この2つは、自然栽培において単なる品種の選択肢ではなく、農業の原点と未来をつなぐかけ橋とも言えるでしょう。
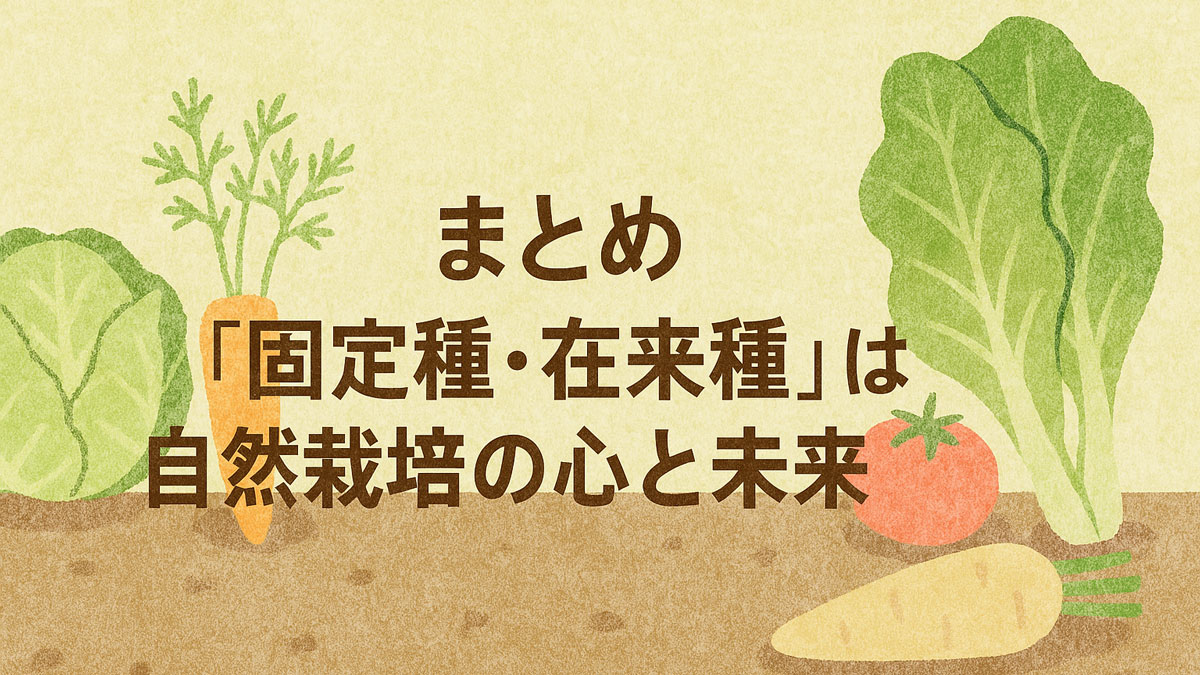
自然栽培の土台としての“固定種・在来種”
本文でも紹介した通り、自然栽培ではF1種のような均一性よりも、ばらつきや個性、多様性が求められます。固定種・在来種はまさにそれに応える存在です。
生育のばらつきや発芽の難しさはあるものの、その過程で「作物と対話する」ような感覚が得られ、育てる喜びが深まっていきます。そして、そうした丁寧な関わり方が、結果として“味の深み”や“地域性”といった目に見えない魅力につながっているのです。
種をつなぐことは文化をつなぐこと
農家だけでなく、家庭菜園や教育現場でも固定種・在来種が注目されている背景には、「種を守ること=文化を守ること」という認識の広がりがあります。
在来種を使った学校教育では、子どもたちが種まきから収穫、採種までを体験し、命の循環を体感します。また、高齢者が昔育てていた野菜をもう一度手にすることで、世代間の記憶が“味”を通じてつながる瞬間も生まれます。
さらに、地域によっては在来野菜を使った加工品開発や観光企画も進んでおり、「タネ」が地域経済やコミュニティ再生の起点となっている事例も少なくありません。
固定種ライフは誰にでも始められる
最後に、自然栽培と固定種の取り組みは、何も特別な農家や専門家だけのものではありません。小さなプランターや家庭菜園からでも、“固定種ライフ”は始められます。
種を蒔き、芽が出て、育ち、実をつけ、そして再び種になる──。この命の循環を体験することこそ、自然栽培の真の魅力です。
今、わたしたちにできることは、ひとつの小さなタネを選ぶこと。そのタネが持つ物語に耳を傾け、土と向き合い、自然と共に育てること。それが、未来の食と暮らしを守る第一歩になるのです。
◎まとめのポイントチェックリスト
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| なぜ固定種・在来種なのか? | 自然栽培と相性がよく、味・強さ・文化を引き出せる |
| 種の価値は? | 単なる品種ではなく、命と地域の記憶をつなぐ存在 |
| 誰でも始められる? | 家庭菜園レベルでも固定種の栽培は可能 |
自然栽培で輝く固定種・在来種の魅力は、決して一朝一夕に語り尽くせるものではありません。しかし、このブログを通じて、「種を選ぶ」という行為が、自分と自然、地域と未来をつなぐ大切な選択であることに気づいていただけたなら幸いです。
タネを選ぶことは、生き方を選ぶこと。あなたも今日から、“固定種のある暮らし”を始めてみませんか?
出典・参考文献情報
この記事の内容は、以下の信頼性のある情報源をもとに構成しています。
-
農林水産省「種子法の廃止と今後の対応について」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kikaku/attach/pdf/index-59.pdf -
NPO法人 種の会「固定種・在来種の野菜とは」
https://tanenokai.org/koteishu-zairaishu -
野口種苗研究所「固定種とは何か」
https://noguchiseed.com/seed/kotei.html -
たねの森「固定種・在来種のタネの販売」
https://tanenomori.org/